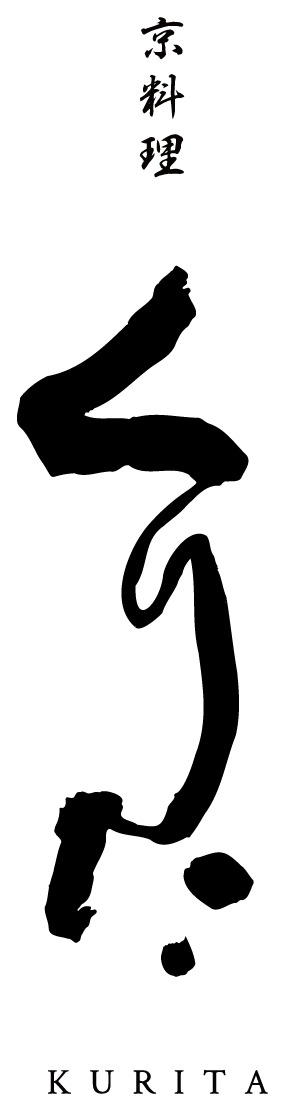くりたのブログ
鰾

これ、なんでしょうか?
薄ピンクで、つるんとしていて、

長さはこんなくらい。
手で持つと、軽い、かるい!
そしてちょっと触ってみると、

ぷにゅっと、しています。
まるで、細長い風船のような、この得体の知れないもの、
これ実は、「鱧(はも)の鰾(うきぶくろ)」、なんです!
いわゆる、浮き袋。
魚が水中で生活するのに、なくてはならない、器官。
漢字では、鰾。魚編に票、と書くんですねー。(これ、知らんかったです!)
そもそも鰾(うきぶくろ)とはなにか?、なんですが、
やはり読みそのまんま、「浮き袋」としての、役割を担う器官であるということ。
ほとんどの硬骨魚類にはあって、
これによって、浮力を調整しているのですね。
ぷにゅっの中身は、もちろん気体(ガス)。
このガスを出し入れすることによって、
浮き沈みを調節するらしいです。
魚によって、当然この鰾の形も様々なんですが、
魚体が長くて細い鱧は、
やっぱり浮き袋も細長い、んですよねー。
しかも、魚の種類によっては、
鰾にこの浮力調節という基本的役割に加え、
音を聴く為の聴力の役割、
音を発するための発音の役割、なんかがある種もあるらしく、
普段ご家庭等での「料理」という観点からは、
ほとんど意識にのぼらない部位ではありながら、
魚にとっては、とても重要な器官、なんですよねー。
それで、店ではこの鰾、
丁寧に丁寧に処理、下ごしらえをして、
お料理の中の一素材、として変身させます!
火が入ると、つるん、ぷるんとした食感がとても面白くて、
大将、この時期ちょいちょい使わはります。
主役、になることはあんまり無いんですけれど(!)、
お料理の中の一員としてちょっと加わると、
ん!?おっ!?と、良いアクセントになって、
その存在感、活きてきます。
登場はお献立にもよりますので、その時々、ということにはなりますが、
ご来店のお客様で、もしお献立の中に登場した際には、
「これかぁ!!!!」と思っとくれやすね。
是非に。
 大将がこのうきぶくろの作業をしていると、
大将がこのうきぶくろの作業をしていると、
なぜかいつも、海水浴のことを思い出します。
浮き袋→浮き輪→海水浴、という、
ただただ単純な連想によるものと思われます。
夏、ですね(笑)